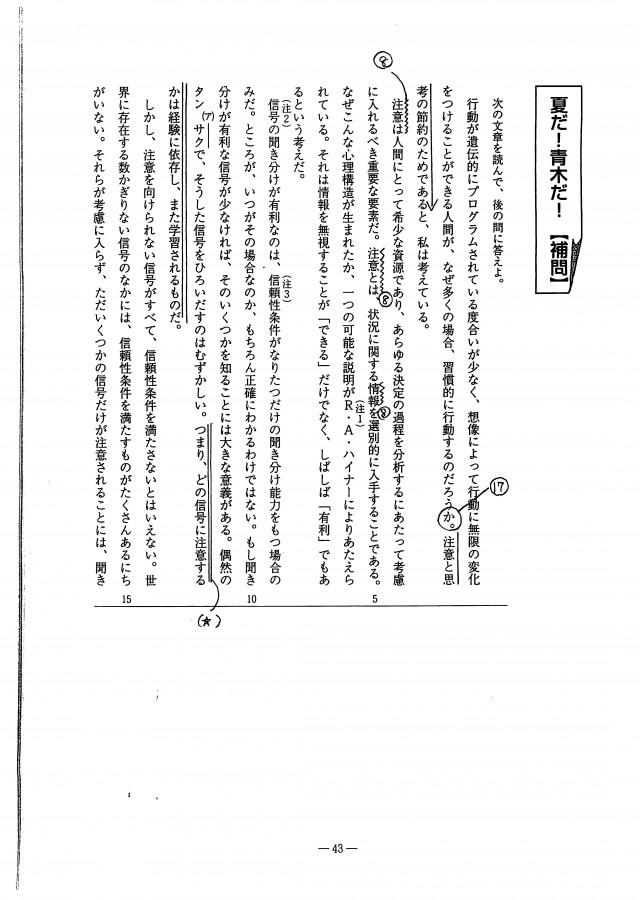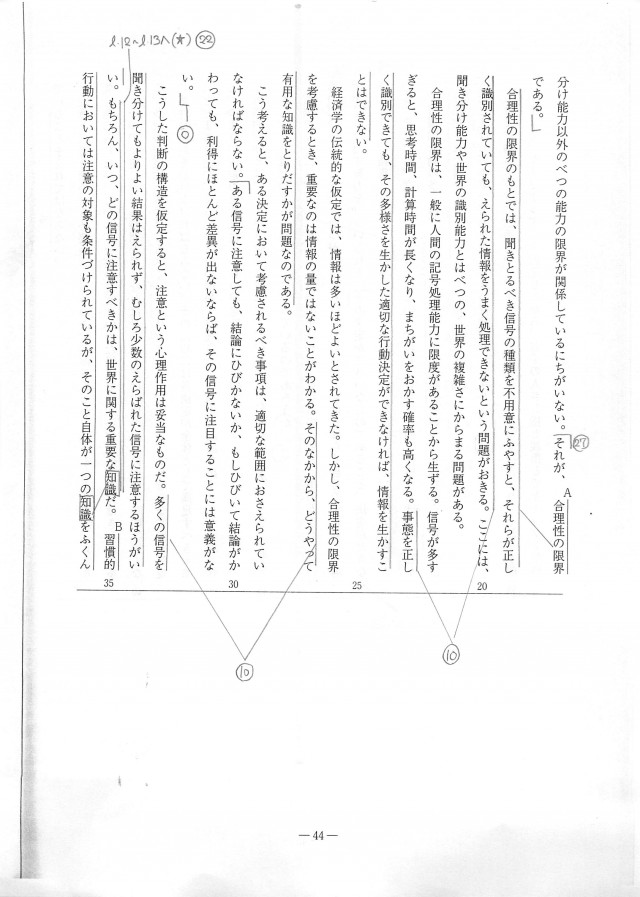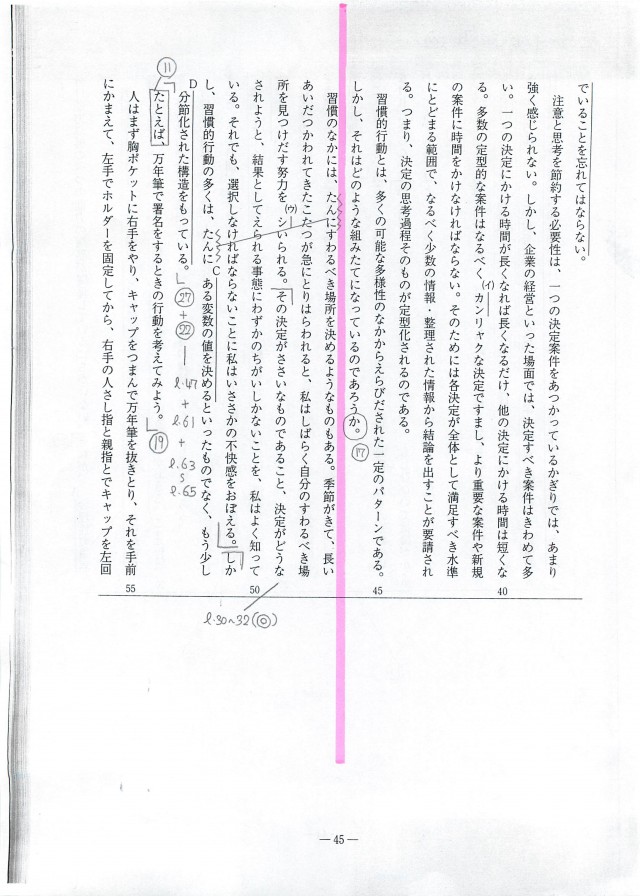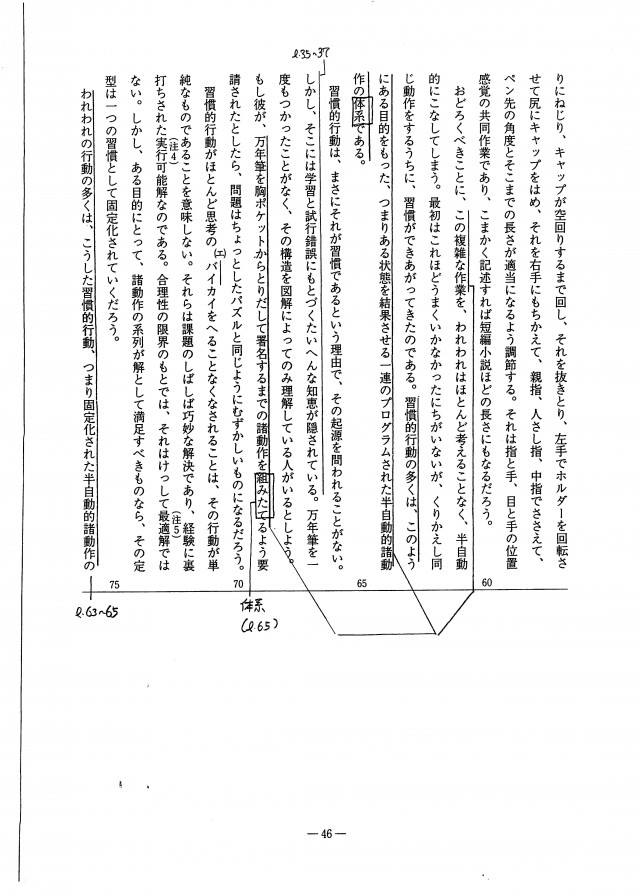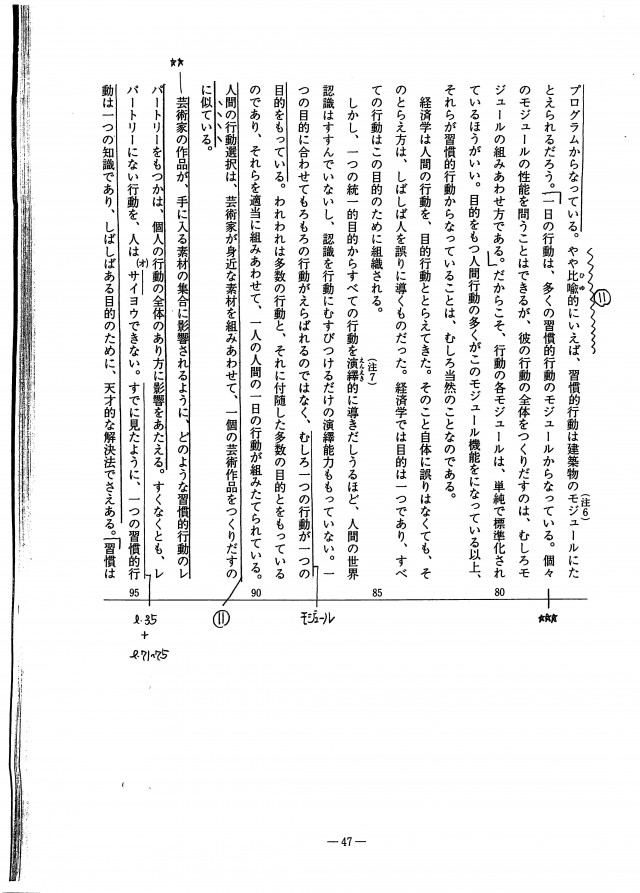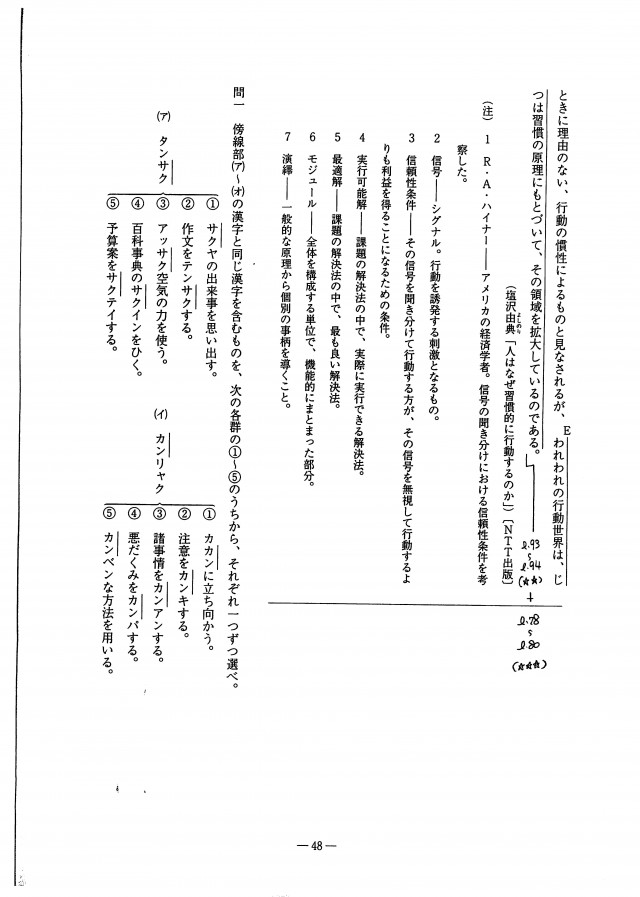【要約】
寺へ参る、その時間的距離は「私」にとっては〈聖なるもの〉に近づいてゆく心の深まりの距離であり、求心状態が作られる過程として大切なものである。またその過程は「私」のとって自己を低める行為のことでもあり、寺に参る際には「私」は自分の心の不完全さや愚かしさを絶えず身に染みて感ずる時に、どれだけ自分を低めることが出来るだろうかと考える。自己を低めることで見えてくるものは、自己と絶対者との関係、あるいは自己と世界との関係であろう。ルネサンス以降は自己を高めようとした時代だったが、中世は自己を低めるということが芸術作品にも及んでいた時代であり、自己を低めることによる敬虔と畏れの心が、逆に美しい物を作った時代であった。
《問1》ア ひな イ せんえつ ウ けいけん キ がらん
《問2》46ページ参照
《問4》(講義で説明済み)
寺に向かって歩む際に、自らの心の不完全さ愚かしさを感じ、自己がいかに低い小さい存在であるかを知る。
【解説補足】
《問3》
A
❶㉗で一文にした後、「このようなこと」=不足情報を明らかにする。
❷「このようなこと」=「戦前の~合わない」を指しているのだが、この中に空欄Bが含まれてヒントになりにくい。
❸そこで、空欄を含む一文と対応する箇所を探すと、「いまだ[ A ]をもたない私」≑28行目「私は敬虔な信者のように心むなしく神仏にぬかづくわけではない」という対応箇所が見つかる。
❹ここからAには「信仰」が入る。
B
❶空欄Aの時と同様に考えると、「私」は「[ B ]的で教養主義的な古寺巡礼」が「合わない」という意味を、この箇所が作っていることが分かるが、私の「古寺巡礼」は、25~26行目に説明がある。
❷そこには「美意識の問題ではない」とある。ということは、「私」が古寺を巡るのはそれらが「美しい」からではないということになる。
❸そこから「審美」が選べる。
《問5》
❶35~36行目を㉗で一文にして考え、対応箇所(神経衰弱式(笑))を探す-近くにないので㉒扱いで、一端保留にし、9段落以降を探してみる。
❷すると45行目に「『個性』や『自我』の解放に生きた無邪気な近代への強い反省」という表現が見つかる。
❸元の35~36行目との対応をチェックすると、「明治以降」≑「近代」、「あまりにも~求めすぎたり~願いすぎた」≑「反省」、「『自我』の確立」「『個性』の伸長」≑「『個性』や『自我』の解放」となってマッチしているのがわかる。
❹そしてそこから設問にある筆者の「揶揄」≑「からかい」と思われる言葉を探すと「無邪気」という言葉が見つかる。
❺つまり、近代以降人間は38行目「(神などに)生かされている」ということを、つまり「中世の心」(64行目)を忘れていることを、あまりにも(54~55行目)「自己と絶対者との関係、あるいは自己と世界との関係」を忘れてしまって、「自己(近代的自我)」を賛美しすぎている点を「わかってねえ~な~」という意味で「無邪気」だと表現したのである。
《問6》
❶《問5》と強い関連を持つ設問である。53行目を㉗で一文にして考えると-
中世という時代-自己を低めようとした時代
VS
ルネサンス以後(近代)-自己を高めようとした時代
という関係が表わされていることがわかる。
❷ということは傍線部は近代以後のことを説明した35~36行目と重なる(対応)。
❸制限字数が10字程度なので、35~36行目は多すぎる。したがってさらに対応箇所を探すと、問5で見たように、これらは45行目に説明がある。
❹そこに「『個性』や『自我』の解放」という表現があり、これは12字であるので「10字程度」に当たる。
《問7》㊟「合致しないもの」を選ぶ。
イ 筆者は6段落で「敬虔な信者」ではないと言いつつ、自らは「自分を低め」るという「中世の心」と同様の感じ方をしている。〇
ロ宗教的創造物、つまり古寺とかを美的鑑賞するのに敬虔な心は必要ない。6段落で筆者は古寺を巡る理由を「美意識の問題ではない」と言っている。×
ハ「地上の距離と歴史を超えて」というのは、つまり「時空を超えて」(自己を低める心が存在する≑普遍的)ということである。筆者が本文で「自己を低める」経験を外国でも経験したり、あるいはポール・クローデル(17行目・33~34行目)の言うことが、道元の述べたこと(32~33行目)と「つながっている」ということからも判断できる。〇
ニ 5段落に書かれている。〇
ホ自己を低めることは、「自己を真空状態にするにしたがって神がそこに入ってくる」とも表現されており、また63行目に「自己を低めることは敬虔であり畏れである」ともある。〇
ヘそもそも筆者が古寺を訪れて感じるのは29~31行目にあるように「自分の心の不完全さや愚かしさ」であり、それを「たえず身にしみて」感じる以上「自己陶酔」はあり得ない。×
《解答》
問3 A ロ B ロ
問5 無邪気(な)
問6「個性」や「自我」の解放
問7 ロ ヘ
《復習問題》
テキスト本文61行目に「まるで自然の『物』のように」とあるが、これはどういうことか。次の中から最も適当なものをひとつ選べ(㊟解答は最下段。スクロールして確認のこと)。
①自己を低めつつ孤高をたのんで
②自ら充足しつつ調和を保って
③輪郭の確かさを誇示しつつ
④制約を退けつつ自由に
⑤個を滅却しつつ超然として
《解答》
⑤(自我、個性、それを作った人は「忘れ去られて」、まるで絶対者(57~59行目)のあわれみによって作ることが可能になったように、という意味)