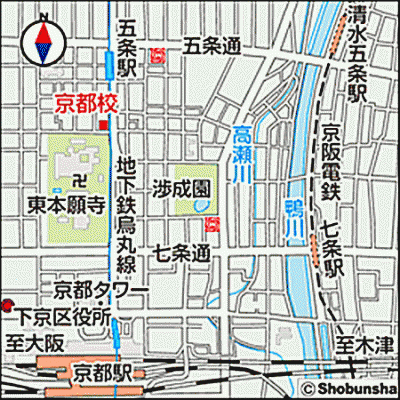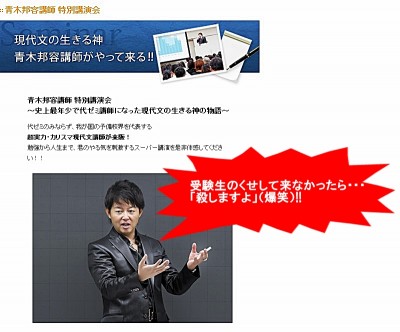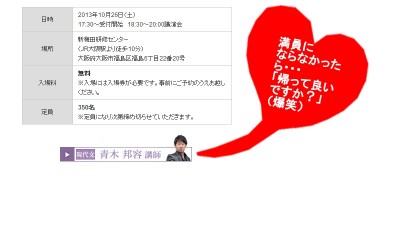《要約》
文化と経済とは対立的に考えられがちだが、経済が生産と消費、供給と需要、販売と購入とからなり、生産・供給・販売は、文化としての生活様式である消費・需要・購入に従属すると言える点で、経済は文化に従属する。その文化は遍在し、それが他地域から憧れられて、取り入れられ普及すると、その地域の文化は文明になる。そうした文明は、文化と異なり偏在し、興亡し、また移動する。文化が中心性と普遍性を備えると、文明になる点で文明の基礎には文化があると言える。近代文明は資本主義として勃興したが、その出生には、プロテスタンティズムに見られる禁欲や、世俗的贅沢、あるいはアジア地域の文化への憧れといった、非経済的・文化的要因があった。特に大航海時代前後においては、黒死病に生命の危機を募らせたヨーロッパは、アジアに胡椒・香辛料を求め、また東南アジアは多文化交流の坩堝であり、ヨーロッパ諸国は東方の物産、特に木綿に魅惑され、やがてそれが経済的理由から買えなくなると、自分達で作りだした。後に産業革命の主軸になるのが木綿産業であるが、その点でまさに文化革命が主導して産業革命が後を追いかけたと言える。こうしてヨーロッパ人の生活危機、宗教意識、またアジアの文明への憧れが、ヨーロッパに人類最初の経済文明をもたらしたのである。
《問7》「文化」は、「経済」を従えて遍在し、他地域から憧れられ、普及して「文明」になる。